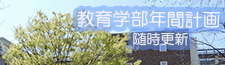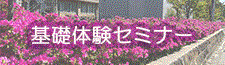第4回だんだん塾講演会
ハヤイはウマイ,記事の基本調理法
|
実施日: 平成24年2月23日(木)14:30~16:00
|
|
会場: 教育学部5F 多目的ホール(517)
|
|
参加者: 36名(教職員を含む)
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(2)わかりやすさの根本は「筋が通っていること」 このようにしてつくられる「良い」記事は,文章の構造がきわめてシンプルになっているから,「見出しの立つ記事」になる。大事なキーワードが浮かび上がってきます。この日学生自身が書いたドリルの文章をもう一度読み返し,自分の述べたいキーワードが入っているか確かめてほしいと言われました。足りないものがあれば付け加える。不必要なものは容赦なくばっさりと取り去る。こうした取捨選択を繰り返して「編集」しながら,起承転結といった流れをつくっていけばよいのですね。 (3) 「自分の引き出し」を見つめてみよう~自己内対話のススメ~
→自分の中に足りないものがあるという人,逆にたくさんありすぎて整理がつかないという人,この悩みはいわば「双子」である。放っておけばよい。それしかない。 一冊ノートをつくってほしい。自分が何を考えているのかをわかるための「引き出しノート」だ。関連づけることもできる。得意なこと,好きなことからで良い。自分の中にあるものを出力してみると,わかってくることもある。とにかく書いてみることが大事。 「自己内対話」がオススメ。煉瓦を一個ずつ積み上げていくようなイメージで。自分だけのしっかりした土台ができる。書いておいたら,しばらく時間をおいて「寝かせておく」ことも大事。以後の変化が面白い。 ここで,文章を書くことについて,偉大な哲学者,ニーチェの言葉を引用されました。
② きちんとした主張をするためには,新聞などの様々なニュースソースから専門知識を得てきちんと学んだ上で,それを整理して自分の考えをつくっていくということでよいか。 →基本的な知識や専門的知識がないと物事が考えられないということは ない。今考えていることが,少し経つと変わってくる。そういう自分を知る ことも大事。そうしてくると,必要な情報を見極める力がつく。情報の集め方も上手になってくる。 ③パーツとペースについて。しっかり情報を集めてじっくり時間をかけて考えれば,やはり良い文章が書けるものなのか。時間配分が難しいのだが…。 →パーツが多すぎると、考えがまとまらなくなることがある。決められた時間内にいろいろ盛り込みたいのだけれどそれが書けないのであれば,そういう自分をまずは認めること。ただ、自分が見通せる範囲で勝負し、曲がりなりにも時間内に書けたものを読んでみると,意外に良いものが含まれていることが多い。書く時にじっくり時間を掛けるのではなく、普段からじっくり考えるということだと思う。 気がつくと,90分を既に超えていました。 |
|||||||||||||||
-----学生の感想-----
|
自分をモニタリングする 心理・臨床専攻3年生 最近,自分の持っている言葉の少なさに気づき,何かしようと思っているところです。言葉の量を増やすために読書をし,気になった言葉や文章をノートに書き留めています。そのノートに言葉が増えるたびに,少しずつは良くなっているのではないかと思っていましたが,今日のお話を聞いて,自分の中から言葉を取り出す作業をあまりしてこなかったことに気づきました。 |
|
自分と向き合う 初等教育開発専攻2年生 普段から書く力や話す力が不足していると感じていたので,今回の講演会を知り,これは参加すべきだと思い,申し込みました。また,読む力をつけるために,前よりも新聞を読むよう意識しており,特に明窓や論説の部分を楽しみに読んでいたので(本当です!),高尾さんの話を聞くことができ,嬉しかったです。 |
自分がどんな「引き出し」をもっているか。なかなか自分自身を見つめることは難しいのですが,高尾さんから,そのヒントや手がかりをもらいました。
しかし,そうはいっても一朝一夕には無理です。少しずつ,こつこつと頑張りましょう。
そして,学生のうちに一度は,新聞へ自分の考えを投稿してみてはどうでしょうか。まずは何か自らアクションを起こしてみましょう。
(文責:福間敏之)







 ①「あれも言いたい,これも言いたい」で結局自分の中で整理がつかなくなってしまう。どうしたらよいか。
①「あれも言いたい,これも言いたい」で結局自分の中で整理がつかなくなってしまう。どうしたらよいか。