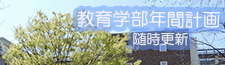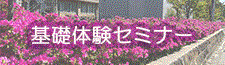第5回だんだん塾講演会
【第5回だんだん塾件C系G系特別講義】
平成18年の教育基本法の改正において,「父母その他保護者は,子の教育について第一義的責任を有する」と初めて規定されました。子どもの健やかな成長を願いながら,適切な指導・支援を進めるには,家庭と学校がそれぞれの役割を果たすとともに相互の連携が必要不可欠です。
そこで,教職を目指す学生として,家庭・保護者との連携の意義を理解し,良好な関係づくりを築こうとする意識の醸成及びその資質の向上を図ることができるよう,今回のだんだん塾を企画しました。
|
実施日:
|
平成27年1月21日 16:15~17:45 |
|
場所:
|
教育学部25番教室 |
|
参加者:
|
教育学部学生48名 教職員7名 計55名 |
| 講師: | 笹原 由乃 氏(松江市立古江小学校 教諭) |
当日の講演の内容について,簡単に紹介します。
|
●演題 「保護者との ほっと コミュニケーション」 ●講義(要旨) ・関わる場面では,誠実で真摯に心を込めて温かく接したい。そしてまずは“聴く”という姿勢から。 ●ミニ演習「保護者からの電話に,あなたならどう答えますか?」 |
○聴講した学生たちのふりかえりの一部を紹介します。
|
私と相手で歩んできた人生も環境も価値観も違うので,相手が年上でも年下であっても尊重しなければならないと改めて思った。また教師という職を考えた時に子どもを教育するためには自分がプロフェッショナル意識を持って過ごすべきだなと思った。子どもによりよい人間関係を築かなければ話にならないと思う。私もたくさんの経験をして人間関係の難しさを実感しているので,本当に日々,学びがあると思った。 |
|
改めて人と関わっていく難しさを感じました。“子ども”と一言で言っても同じ子どもは一人もいないし,背景として持っているものも異なります。さらに表に出てくる言葉や行動だけが全てではないと思います。それでも教師は子ども達とよりよい関係を築かなければならないので,本当に大変だと思います。また保護者も子どもと同様に難しいとは思いますが,同じ方向性で頑張っていけるとも思いました。 |
|
この講演を通して,保護者との関わりに対してのイメージが変わりました。今までは教員の仕事の中でも保護者との関わりは難しいものであり,あまりいいイメージを持っていませんでした。しかし,今回のお話の中で保護者との関係づくりの大切さを実例とともに聞かせていただきながら知ることができました。また,保護者の方の気持ちを大切にすることも必要なのだと感じました。そのために特に「聴く」ことを大事にしないといけないことが強く心に残りました。先生と保護者,どちらとも子どもを大切にするという思いを持っているので,助け合うことが大事だと思いました。 |
|
保護者の方とよい関係を築くことが子どもの教育環境を大きく変えることが分かりました。子ども一人ひとり,そして保護者一人ひとりにそれぞれ背景があり,まず聴くことを通してそれでもできるだけ汲み取って言葉をかけなければならないと思います。気持ちが一度でも離れてしまうと近づくことがなかなかできないのではと,話を聞いた後ですが不安に思うことはたくさんあります。それでも失敗や苦い経験を重ねてその苦しさを受け止め耐える,自分を振り返る冷静さも私には必要だなと,これからの大学生生活で自分がどうあるべきか見つめる良い機会となりました。 |
多くのご経験に基づいた具体的な事例を通して,保護者との連携の意義について大変分かりやすくお話ししていただきました。
また,終わりには,失敗から学ぶことが多々あること,そしてその学びから得たものやつながりが,何より教師としての喜びや醍醐味である,とエールを送っていただきました。
受講した学生たちにとっては,これまでの学びを振り返りながら,今後に向けて新たな視点や課題意識を持たせていただけたように思います。