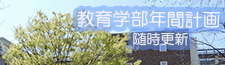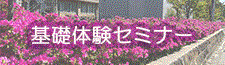第3回だんだん塾講演会
【特別支援教育 講演会】
これまで,学校教育実習や基礎体験活動で多くの子どもたちと関わってきている学生たち。臨床・カウンセリング体験領域の授業でも,様々な子ども達に対する理解,相手理解に努めてきました。しかし,どのように関わっていくとよいのか,戸惑ったり,困ったりすることも少なくありません。
そこで,実際に学校現場で子どもたちと関わっている先生に,特別支援教育の観点からお話をお聞きする機会をもつことができました。お越しいただいたのは,現在,松江市立古志原小学校にご勤務の吉野先生です。これまで,小学校や養護学校,教育委員会,県教育センターなど,様々な場所でご活躍です。生活や学習につまずいている子どもたちの現状とその対応について,身体の発達の側面からお話いただきました。
|
実施日:
|
平成26年12月17日 14:30~16:00 |
|
場所:
|
教育学部25番教室 |
|
参加者:
|
教育学部学生78名 教職員11名 |
| 講師: | 吉野 晃子 氏(松江市立古志原小学校 教諭) |
当日の講演の内容について,簡単に紹介します。
|
●演題 「目の前の子どもの体をよく見よう!~いろいろなつまずきの背景を考える~」 ●内容の概要 |
○聴講した学生たちのふりかえりの一部を紹介します。
|
自分が小学生の頃,クラスに全く宿題をやってこない子がいたことを思い出しました。先生がどんなにやってくるように言っても,全然宿題をやってきませんでした。当時の自分はその子にやる気がないからだと思い,「何でやってこないのか」とその子に怒っていました。でも,今日の話を聞いて,その子にも何らかの事情があったのかもしれないと思えて,悪いことをしたかもしれないと思いました。 |
|
教育実習及び学習支援で落ち着きのない子どもを見てきました。その時,そのような子どもたちは,人の話を聞くという経験が足りていないことが原因であると考え,話の聞き方や姿勢というものは指導を行うことで改善されると安易に考えてしまっていました。しかし,私の指導を受けた子どもたちは「わかっているけどできない」というようなもどかしい気もちのみが残ってしまっていたのかもしれません。「子ども理解」を指導における根底に置くために,子どもの体を見るという方法に出合えたことで,さらに有効な指導を行えるようになりたいです。 |
|
私は田舎で育ち,たくさんの外遊びをしていました。川や山に行って探検したり,学校の休み時間にはカンケリやテンカ,オニゴッコをたくさんしたりして過ごしました。何気ないこれらが,とてもいいことだったんだと思いました。現在,子どもたちの遊びの状況が変わった今,学校で私たちができること,やっていかないといけないことを,保健体育を専攻する者として,もっと考えていきたいと思いました。 |
|
発達段階に合わせて子どもを見るということは,これまで態度などの雰囲気的なもので感じていたように思います。しかし,はっきりと子どもの動き,体の使い方で見ることもできるというのは,とても画期的でいいなと思いました。その改善のために,一つひとつの動きを積極的に取り入れていくことがよいということも,これからどんどん知っていきたいと感じました。 |
現場における具体的な事例をもとに,写真でその場面を多く示していただきながらのお話でした。また,その実際の様子を理論に結びつけて整理していただき,とても分かりやすく学ぶことができました。
「体の力」の大切さ,そして,それらが時代的な背景から充分に身に付いていないために,思うように学習や活動に取り組めない人がいること,それは一部の子どもたちの話ではないことに気付くことができました。体と心は相互に関係し合っているということを再認識しながら,単なる精神論だけで指導するのではなく,「体の様子は見える」からこそ「体の力を見える形で工夫して,伸ばす」方法に驚きをも感じたことと思います。
学校教育実習や基礎体験活動で子どもたちと関わってきている学生には,お話いただいた子どもたちの様子やその時の対応の困り感などについて思い当たることが多かったようです。あらためて,その時の自分の困り感や対応の仕方,一方の子どもたちの様子や思いなどについて振り返る機会となりました。その上で,これまでイメージ的にしか捉えていなかった子どもの教育ニーズを知る具体的な一つの手法を知ることで,自分自身の子どもを見る目,理解しようとする姿勢のあり方を再度考え直し,これからの子どもとの関わり方をよりよいものにしたいと決意を新たにしました。